共済制度は、公務員や教職員などの職域共済だけでなく、農業協同組合(JA共済)や生活協同組合など、さまざまな団体が運営している仕組みです。
障害のある方やその家族に関係する制度は大きく分けて次のようなものがあります。
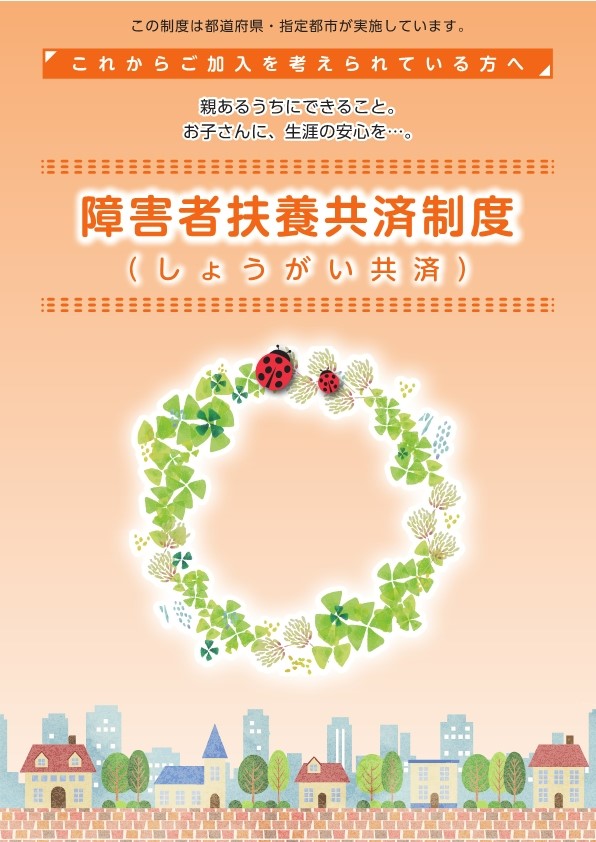
- 1. 職域の共済制度と障害
- 2. JA共済(農協共済)
- 3. 生活協同組合の共済(例:コープ共済)
- 4. 障害者向けの特別な共済制度
- 5. 民間保険との違い
- 障害がある本人が入れる共済について
- 「本人が加入できる」かどうかを確認するためのポイント
- 障害のある子どもの将来に備えるための共済・扶養制度について
1. 職域の共済制度と障害
国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済
→ 基本は公的年金(国民年金・厚生年金)と同様に「障害年金」の給付が用意されています。
→ 在職中の事故や病気で障害を負った場合、障害給付や傷病手当金が支給されることがあります。
2. JA共済(農協共済)
- 「生命共済」「医療共済」「介護共済」などがあり、障害を負ったときの給付も対象になります。
- 例えば「生命共済」では、不慮の事故や病気で所定の高度障害になった場合、共済金の全額支払(以後の掛金免除)が行われる仕組みがあります。
3. 生活協同組合の共済(例:コープ共済)
- 掛金が比較的安く、加入しやすい。
- ただし、障害のある方が新規加入する場合は制限があることも多い(加入時に健康状態の告知が必要)。
- 既に加入している人が障害を負った場合は、医療保障や死亡保障の給付が受けられる。
4. 障害者向けの特別な共済制度
心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)
→ 全国の自治体が行っている制度で、障害のある子を持つ親が掛金を払い続け、親が亡くなったときに障害のある子へ終身で年金(毎月2万円程度)が支給される。
→ 障害者本人の将来の生活保障を目的とした代表的な制度です。
5. 民間保険との違い
- 共済は「相互扶助」の仕組みなので、掛金が比較的安い。
- 一方、既に障害を持っている人の新規加入は難しい場合が多い。
- その場合は、障害の有無にかかわらず利用できる「しょうがい共済(自治体制度)」や、公的な障害年金を中心に生活設計を考えることが重要。
障害がある本人が入れる共済について
障害のあるご本人が新規で加入できる共済制度、あるいはその可能性がある制度は、調べたところ「保護者が加入するタイプ(心身障害者扶養共済制度)」が中心で、障害本人が直接加入できるものは限定的・要審査というものが多いです。
「本人が加入できる」かどうかを確認するためのポイント
1.共済の「告知書」・「健康状態の告知」の要件
既に障害があることを申告しなければならないか、それをどう評価するか(例:重度か、治療中か、将来進行性か等)。
2.障害の種類/手帳の等級・程度
たとえば身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、どの種類や等級が対象になるか。制度によって範囲が限定されていることがあります。
3.加入可能な年齢
制度によって「加入時65歳未満」「年度始めの年齢で判断」など制限がある場合があります。
4.過去・既存の障害の扱い(既往の障害)
加入申込前から持っている障害をどのように扱うか(加入否認・保障制限・掛金割増など)。
5.自治体制度 vs 民間共済
自治体の共済(心身障害者扶養共済制度など)は「保護者加入」が多く、自分自身で加入するタイプではないです。
民間共済団体/JA共済などは本人加入が可能な共済プランがある可能性が高い。
障害のある子どもの将来に備えるための共済・扶養制度について
心身障害者扶養共済制度(障害者扶養共済制度・しょうがい共済)
いわゆる「親なき後」など、保護者にもしものことがあったときに、障害のある子どもが生涯にわたって一定の年金を受け取れるようにする制度です。
都道府県・指定都市自治体が条例にもとづいて実施しています。
厚生労働省も案内を出しています。
注意点/デメリット・限界
将来に備える上で、この制度だけで十分とは限らないので、併用を検討することをおすすめします。
1.保護者の加入条件がある
健康状態・年齢・住所などで条件があり、保護者が加入できないケースがあります。
2.支給までの条件・口数の制限
2口までなどの制限があり、支給額も口数で変わるが、生活費全体を賄うには足りないケースが多いです。
3.将来の生活コスト・インフレ対応が不確実
年金額が固定であったり、制度見直しがある可能性があります。
4.制度の継続性・運用自治体間で内容に差
自治体ごとに掛金金額・給付額・加入の対象・免除制度などが異なります。引越ししたら制度が変わる可能性あり。加入期間の通算を認める自治体もありますが確認が必要。
5.税制・福祉制度との兼ね合い
この年金が所得認定・課税対象になるかどうか、生活保護など他の福祉制度との関係を調べておく必要があります。
姫路市の例では「所得税・地方税・生活保護の収入認定にならない」などの自治体があるようです。
他に検討しておきたい制度・準備
共済制度だけでなく、将来の安心のために以下もあわせて検討すると良いと思います。
- 障害年金(基礎年金/厚生年金など)
- 障害等級に応じて支給されます。初診日や保険料納付要件があります。
- 障害者手帳取得 →さまざまな行政サービス・福祉サービス・割引などを受けやすくなる。
- 福祉・医療・介護制度の利用(療育・訪問支援・障害児通所施設等)
- 生命保険・信託・保険外の貯蓄を活用したプランニング
- 成年後見制度や 財産管理・遺言等、親亡き後の法的準備